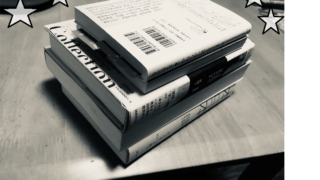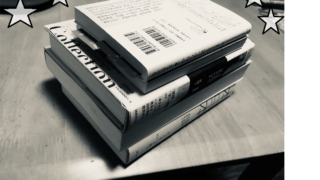フリー素材ぱくたそ(www.pakutaso.com)
フリー素材ぱくたそ(www.pakutaso.com)更新履歴:2020/07/10 前置きの追加・レイアウト修正
「全集」
読者のみなさんは、この言葉にどういう印象を受けるであろうか?
無駄に大きい、重い、高い
もしかしたら、今の若い人はあまり良いイメージを持っていないかもしれない(自分も若いが)。
それでも、昔は家に全集を置いていることがステータスとなっていた時代があったらしいのだ。
現に私の実家にもたくさんの文学全集が置いてある。
正直、私は全集で読むより文庫や単行本サイズで読む方が好きなのだが、一つだけ全集は素晴らしいと思うことがある。
それは、月報だ。
著者の身近な方々、あるいは作家仲間が、あれやこれやと著者について語ったものをまとめている。
真剣に語られたものから、仲間ゆえのジョークなども含め、非常に内容が面白い。
そして今回ご紹介する本は、この月報がキーワードになっている。
全集に挟まっている小冊子は魅力の宝庫
講談社文芸文庫「個人全集月報集」は、とても面白い企画だと思った。
この本は、「安岡章太郎」、「吉行淳之介」、「庄野潤三」の全集に挟まっている小冊子を、一冊の本にまとめたものである。
小冊子は月報と言われるもので、繰り返しになるが、著者に関わってきたいろいろな人たち(作家など)が、著者について解説しているのが特徴。
作家からみた、著者の性格や行動様式が赤裸々に語られているため、著書からしか情報が得られなかった読者にとっては、非常に楽しめるものだ。
人によっては、月報のために全集を買う、という強者もいるかもしれない。
逆にいえば、全集を買わなければ手に入らないものなので、この「個人全集月報集」は私のように「全集を買うのはちょっとお金が厳しい・・・」という方に最適だ。
作家からみた作家の面白さ
安岡章太郎、吉行淳之介、庄野潤三は「第三の新人」と呼ばれる方達で、芥川賞受賞歴のある名作家だ。
私はこの月報集を読み終えて、今まで自分の知らなかった、著者のパーソナルな部分を知ることが出来た。
そんな訳で、全集の著者別に少しばかり解説していきたいと思う。
皆さまがこの月報集を手に取る機会となれれば幸いだ。
安岡章太郎
安岡章太郎は、1953年に「悪い仲間」・「陰気な愉しみ」で芥川賞を受賞し、1959年に「海辺の光景」で芸術選奨と野間文芸賞を受賞している。
数々の賞を受賞した後、その経歴が認められて、2001年に文化功労者に選ばれる。
月報を読む限り、安岡章太郎さんは、とても会話の上手な方であったらしい。
佐伯彰一さんは、本書で以下のように、安岡さんのことを語っている。
個人全集月報集 p.95
安岡という人物は、いざ顔を合せて話し出すと、なかなか話し好きで、話題も豊富で、そして意外なほど断定的、積極的な語り手だと判明するのだけれど、しかし一たん離れて考えると、まず念頭に浮かぶのは、引っこみ思案で出不精な、とかく殻の中に身をすくめて不快な外界との接触など避けようとする、いわば日本的な私小説か気質、
「花祭」や、「とちり虫」を読んだ私としては、この文章を読んで、「なるほどなぁ・・・」と思ったものである。
まず、話好きで、話題が豊富という点は、「とちり虫」のようなエッセイでその真価を発揮している。
「花祭」における、子供の秘めた欲求の描き方は、引っ込み思案で出不精、外界との接触を避けようとするという点があるからこそ、書けたものかもしれない。
トラウマや劣等感を内に抱えながらも、それがむしろ安岡章太郎の人間的魅力、会話力に繋がっているのだと思う。
「花祭」については、以下の記事で感想を書いているためぜひ読んでいただけたら嬉しい。


吉行淳之介
吉行淳之介は、1954年に「驟雨」で芥川賞を受賞している。
そして、数々の文学賞選考委員も務めた人物である。
吉行淳之介さんは、相手に配慮することを忘れない、やさしい人であったらしい。
個人全集月報集 p.54
私は時々吉行を傷つけやしないかと気にかけることがある。それは吉行自身が絶対に人を傷つけることはしまいという配慮をもち続けているように思えるし、だから傷つけられることを許さないからである。もっとも信用の出来る間柄のことである。
この部分に、私はすごくドキっとしたのを覚えている。
私はなるべく、努めて人を傷つけないように生きようとしていた。(そんなことは不可能だったが)
しかし、それと同時に、人に傷つけられた瞬間、その人のことを絶対に許せないと思う自分がいたのである。
自分がしないということは、それを他人がすることを絶対に許さないということと、同義だった。
そういった共感が出来ただけでも、本書を読んで良かったなと思う。
吉行淳之介さんは、異性関係も豊富に経験してきた人であったようだ。
これはとても納得で、「夕暮れまで」における男女関係の描写は、とても秀逸で、豊かな経験のある人ではないと書けないだろう。
庄野潤三
庄野潤三は、1955年に「プールサイド小景」で芥川賞を受賞し、1956年には、名作「夕べの雲」で、読売文学賞小説賞を受賞された。
庄野潤三さんは、義理堅いすごく真面目なお人であったようだ。
個人全集月報集 p.251
百通を越す庄野の手紙が出てくる筈で、私もいまと違って筆不精ではなかったのでそれに見合う数の手紙が彼の手もとにあることになる。
彼は当時から家庭を大切にする人物だったから、あまり酒場などには足を踏み入れなかったようだ。
家族を大事にし、仕事熱心なところが、非常に著作に現れていて、「夕べの雲」では、家族との時間を文学として昇華し、山の上での生活を、流れるような時間の経過と共に描いている。
父親の貯蔵している本の中に、庄野潤三集があったため、今後はそちらも読んでみたいと思っている。
現代の産物に感じること
月報を読んで、もう一度第三の新人の本を読むと、やはり今発売されている本とは雰囲気が決定的に違うように感じる。
良い悪いの問題ではなく、生々しさが違うのだ。
小説の生々しさとは、どこまで人間の行動原理、内面に話をフォーカス出来るかということが大きく関わってくる。
同じ行動を文章にしたとしても、作家によって全く違う描き方をするのだ。
私は以前から不思議に思っているのだが、現代を象徴するもの(携帯やパソコンなど)が登場してくるとなぜか現実感が離れていくのである。(それはそれで好きなのだが)
携帯やパソコンというのは個人のアイデンティティを消し去ってしまう産物なのではないかと考えてしまったこともあった。
現代を生きているのに、現代の産物に実感が持てないのはなんとなく寂しく感じてしまう。
第三の新人の著作を読んでいると、そうした冷たさを温めてくれる、なんともいいがたい心地よさを与えてくれるのである。
お勧め関連記事